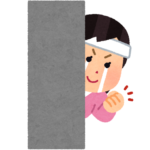【育児の現場にて】
『保育士 「お餅さん」へのインタビュー』
保育士である「お餅さん」は
長く保育の現場で子供たちと向き合ってきました。
お餅さんには 一人娘の「丸ちゃん」がいます。
お餅さんはご本人が 機能不全の毒親に育てられ親からの
壮絶な存在否定と虐待を受けてきた生い立ちから
半ば執念のように「心を育む保育」を追い求め
勉強し、保育の現場で実践し多くの子供たちの心を救って来ました。
お餅さんから 保育現場での現実のお話と
子供との向き合い方について伺いました。
幼い子供さんと向き合っていると
必ず訪れる恐怖の現象【イヤイヤ】
何を言ってもイヤイヤ。 オモチャもお菓子もママも この世の全てを拒絶する恐怖のイヤイヤ。
なんじゃこりゃ どーすりゃいいのよコレ…。
結論:【イヤイヤは成長の証です。イヤイヤ出来た成長を誇らしく感じて】
何を言ってもイヤイヤ、物を投げてしまったり、泣き止まなかったり、スーパーでお菓子買って、
おもちゃ屋でおもちゃ買ってと主張するお子さんの姿に戸惑った事はないでしょうか?
何故子どもにイヤイヤ期があるのでしょう?
それは、自己が芽生え始めたけど、まだ自分の気持ちを言葉や行動で表せなかったり、
自分の気持ちに気がついていない事が一つ上げられます。
そんなイヤイヤ期に子育ての中で、誰もがぶつかり、悩むお母さんも多いのではないでしょうか?
そして、子育てはお子さんと1番一緒にいる時間が長いお母さんが
「なんで、この子は親の言う事を聞かないのだろう?」
「私の子育てが間違っていたのではないか?」
とご自身を責めてしまうお母さんもいるかも知れません。
でも、決してそんな事は無いのです。
イヤイヤ期は
お子さんが成長していく上でとても大事なプロセスです。
「自分を見つける時間」
まだ自分の気持ちに気がついていなかったり、自分の気持ちを言葉で表現できないお子さんが、自分を見つける大切な時間だからです。
そんな時は、
まず、お母さんがお子さんの気持ちに共感する「声かけ」をしていってあげてください。
「そうかぁ、そうかぁ」
「これが嫌だったんだね」
「こうして欲しかったんだね」
というような具合です。
このような声かけをしていく事で、子どもは上手く自分の気持ちを表現できないジレンマを解消していく事ができますし、自分の気持ちに気がつく一歩となっていきます。
そして、
「お母さんは僕の気持ちを分かってくれるんだ!」
「僕の気持ちに気がついてくれるんだ」と
お子さん自身が認識でき、それはやがて、僕は愛されている存在なんだ。
必要とされている存在なんだという自己承認、自己肯定が育まれていきます。
このイヤイヤ期は「子ども自ら自分を見つける大切な時間であるという認識」をお母さんが持ち、大らかな気持ちを持ち過ごしてみてください。
どうか
「私の子育てが悪かったせいで、この子がこんな行動をするんだ」と
ご自身を責めないでください。
お母さんの笑顔は子どもの愁いの全てを除く魔法だからです。
「笑顔の魔法」これを必ず覚えていてください。
イヤイヤ期には終わりが必ずあります。
子どもが自分の気持ちを上手く表現できるようになってきたら、落ち着いてきますので、それまで待ってあげてください。
そして、もう一つ大切な事は
「イヤイヤ=ダメな子と捉えない」という事です。
親の言う事を聞く子がいい子という概念があると
どうしてもイライラと自己主張し、自分の気持ちに気付こうとしている子どもに、ついつい
「言う事を聞きさないー」
と押さえつける言葉を発しがちになってしまい、お母さん自身もせっかく頑張って子育てしているのに、自己嫌悪に陥りやすくなってしまい、子どもの1番エネルギーになる笑顔を失ってしまうからです。
そして、お子さん自身も、イヤイヤして怒られてしまうと、
「自己表現しては いけない」という認識になってしまいがちだからです。
「クッション」
クッションなど柔らかい物を押さえつけていると
形が潰れててしまいます。
離せば元の形に戻るのかもしれませんが、ずっと押さえていると弾力性がなくなりぺっちゃんこになってしまいます。
それと一緒でお子さまの心もずっと
「〇〇してはいけません」
「〇〇しなさい」
という風に押さえつけてしまっていると
本来の自分の心の形を見失いがちになってしまうので
子どもが自分を見つける時間を大切に大らかな心で待ってあげてください。
かと言ってお母さんも人間ですから、イライラしてもまた、当たり前です。
子育ての中、イライラした事が一度もない人なんていないでしょう。
イヤイヤは子どもの自分を見つける大切な時間なんだと思っても
目の前で自己主張するお子さんに対して
イライラしてしまう時もあると思います。
そんな時に無理に関わろうとしても
イライラが増してしまう懸念がありますので
子どもから少し離れて
気持ちが落ち着くのを待ってから関わるのも1つの方法です。
子供さんが初めてハイハイした日
子供さんが初めて歩いた日
喜びに震えたはずです。
【イヤイヤ】も それらと全く同じ 子供の成長の証なのです。